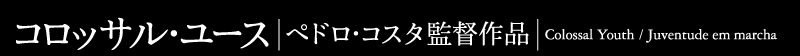
『コロッサル・ユース』の中でヴェントゥーラが訪れるたくさんの場所の中で、他とは異なる場所が1つある。それがグルベンキアン美術館だ。それは多すぎて、彼自身でさえ何人いるか分からない息子たちの1人(この場合、美術館の警備員)に会いに来るという、よくある口実だった。この時は、舞台装置がかなり違った。彼がレントとシェアしている、影の中に溺れた小屋とはまったく違い、新たな住居の真っ白な壁とも違い、ルーベンスとヴァン・ダイクの間に、寡黙な巨人を見つけるのだ。ペドロ・コスタが、このつながりについて説明している。それは愉快で明確だ。ヴェントゥーラ(俳優の名前であり、彼が演じる登場人物の名前)がこの場所に来たがったのは絵への情熱からではなく、彼が石工だった時、絵がかかっている壁の建設にかかわったからだというのだ。
フランドル派の絵画の中の多くの金持ちたちの近くに、ならず者を置くことで、このシーンはコスタが20年近くやってきた仕事の再開となった。彼の言い回しによって、彼が現在の映画界において、非常にユニークな位置を占めていることが十分に理解できる。彼は、最低限必要なものを得るために、いつも苦労しなければならない人々に、アートの快楽を与えることに打ち込んでいる。このポルトガル人の監督は、特にリスボンで最も貧しい地区の1つであり、今は取り壊されたフォンタイーニャスで、貧しい人、ホームレス、放浪者、麻薬常用者を撮っている。彼は、ここで3部作『骨』、『ヴァンダの部屋』、『コロッサル・ユース』を撮った。
『コロッサル・ユース』は基本的に、大きな建築物を半分にしたものだ。芸術の主張は、その中にきちんとした土台を作り、家を見つけなければならない。ヴェントゥーラと彼の家族に一時的な囲いを与えるだけでは十分ではない。彼らは屋根を与えられなければならないのだ。その下でならくつろげて、連帯感を持て、自分たちの過去と伝説に近いと感じられるような屋根をだ。これこそが1972年、カーボヴェルデ人地区に到着して、彼を迎え入れた掘っ立て小屋で、ヴェントゥーラが感じること(またはフラッシュバックに従えば感じたこと)だ。コスタは非常に孤独だが、彼が同時代人たちと分かち合う映画の側面が少なくとも1つある。ある者にとっては女神で、ある者にとっては妖精であるアートと家の根拠を伝えるのに関心を持っていることだ。アラン・レネに似たジャ・ジャンクーや、フィリップ・ガレルに似たガス・ヴァン・サントは今日、登場人物に"土の上にある家"を与えることを願っている。『ラスト・デイズ』のブレイクの最後の願いのように。彼らすべてが、モニュメントと廃墟の間のどこかに、自分たちの建物を置いている。ゆえに『コロッサル・ユース』のたった1つの違いは、この映画がアートを取り巻く環境と日常生活のそれを評価し、その間ずっと、その2つの混同を拒否していることだ。彼のフィクションの源に横たわるのは、ドキュメンタリーへの忠誠か?例えばフォンタイーニャス地区の取り壊しや、その後の住民の移転など。確かに彼にとって、それは大切だ。しかし我々にそれを思い出させることは、作品をそれ自身に戻すことであり、この源もまた、あるいは何よりも前に映画であることを忘れないようにすることであり、コスタの映画の進化において、『ヴァンダの部屋』によって守られた明白な役割に戻ることである。
『ヴァンダの部屋』には2つの意味がある。『コロッサル・ユース』との2部作の1作目であり、ジャニーン・バザンとアンドレ・S・ラバルトによるテレビシリーズ『Cinéma, de Notre Temps』のため、2001年に作られた『Cinéastes』の"前編"でもある。フォンタイーニャス地区が取り壊される直前に撮られたドキュメンタリーの中のヴァンダの部屋と他の設定を、ストローブが『シチリア!』の新バージョンを編集しているフレノワという"たまり場"とリンクさせているという、混乱させる類似性だ。場所の小ささと淡緑色の壁、外に向かってはめったに開かれないこと、それにヴァンダとダニエル・ユイレという2人の魔女の外見がかなり似ていることまでがリンクしている。やることまでが似ている。ニューロはテーブルを磨き、ジャン=マリーは玄関の端を、脚で掃除する。ジャン=マリーがおしゃべりして、ダニエルが物事がうまくいくよう確認している間、ヴァンダと彼女の妹ジータは何もしてないように見えるが、彼女たちの素振りは同じ必要性を持っているように見える。ジャン=マリーのおどけたコメントが、カットの決定に自由を与える。それと同じくヴァンダがパラパラめくるのは、まさに世界の厚さだ。彼女は2つの住所の間にこびりついた1グラムの麻薬を探して、電話帳のページをこする。しかし一方で、『ヴァンダの部屋』と『映画作家ストローブ=ユイレ/あなたの微笑みはどこに隠れたの?』の近さは、すべてを一度に、あまりにも簡単に解決してしまったかもしれない。編集者と麻薬ディーラーが対等であると証明したなら、映画は未来のために、これら矛盾の完ぺきなハーモニーを壊すため、アートと存在の忍耐を生み出すべきだ。彼はどこか別の場所、『コロッサル・ユース』へ行かなければならなかった。彼は明らかに、フォンタイーニャスの住民たちの追放後、新しい家を見つけるという責務から、そうしたのだ。しかし彼は、それ以上のことをした。自分が初めに作った3本の長編映画『血』、『溶岩の家』、『骨』の中の要素と再びつながって、パーソナルなタッチを加えたのだ。
なんという驚きだろう。我々はコスタが、『骨』の撮影のおかげで、どんなに飽和状態になったことかと言いながら、この時期のページをめくったと、しばしば語ったことを忘れていない。チームで働くことの重圧からくる疲れ、スタッフたちとあれこれ話し合うが、映画については何も話さずに時間をムダにすることへの嫌悪。それに続いたのが、ミニDVを使って1人で、または数人の人たちと撮る、そして毎日撮影するためにデジタル機材の可能性を利用する、低コストのラッシュを撮りためる(『コロッサル・ユース』の数字は、1年半、週6日に渡る撮影で350時間)、スタイルが決まっている人間、労働者階級のアーティストになるという決断だった。コスタは自分の初期の作品を厳しく批判する。彼は「映画は私を裏切った」と言っている。それは間違いなく、『血』、そして『溶岩の家』では、空気が少しでも動くのを許すことのない、映画愛好家の練習で満足していたことを意味している。
しかし『コロッサル・ユース』では、その映画の何かを復活させている。見せかけだけの熱意、ハリウッドのクラシック映画時代をマネしようという望み(ターナー、フォード)、"あのころの"映画が喜んで演じていた、フィクションとオマージュ間の近さなどだ。ヴェントゥーラの子供が国勢調査を拒むように、『溶岩の家』のカーボ・ヴェルデ島には、30人の息子がいると公言する老人が住んでいる。そのうちの1人で作業員のレオンは、倒れた後、深い昏睡に陥る(他の韻:ヴェントゥーラがレントに練習させる、ロベール・デスノスにインスパイアされた手紙からの引用、そしてダンスの途中での叫び声"Juventude em Marcha!(訳注:『コロッサル・ユース』のポルトガル語題名)")。『血』の物語は、11歳のニノが、奇妙な取引の対象となるところから始まる。『骨』でも、非常に若い父親が自分の赤ん坊を、誰でも(看護婦、友人、死)いいから、あげようとする。我々が作って、荷物のように持つ子供、引き受けるか捨てるかする子供、生から死へと持って行く子供、錯乱状態にある家族史、"子供の幽霊"、これがコスタによるフィクションだ。彼のフィルムメーカーとしての最初の作品は、ポルトガルのテレビのための子供向け映画シリーズだった。寓意が分かるだろう。出産は、貧乏人に与えられた唯一の傑作なのだ。多すぎる子供は、どんな生命も余計なものにつながるという証拠だ。邪魔な新生児の死につながることさえある。
では彼はなぜ、10年間顧みなかった神話的な脚本に戻ったのだろう? 答えは簡単で、この映画のもともとの題名の中にある。コスタは若さの運命、前に進むことのチャレンジ、落ちた王子が堂々と存在しているフレームワークのラインを変えることを、ヴェントゥーラに任せたかったのだ。この委託は、同時にフィクションの気ままさであり、その作り事であり、映画が、そのアートの欲望をドキュメンタリーの真実に与える方法、つまりヴェントゥーラのみによってコントロールされる、自分の家から放り出された人々のことである。
絵画は頂点のしるしである。新しい地区の白い壁は、他のことを意味する。裸の壁は疑いなく歴史の欠如だが、少なくとも未来の希望に見える。コスタが、自分の作品とその不在を調整し、自分の武器を磨き、『シチリア!』の粉砕機の抒情の高まりを写真ごとに聞きながら、自分の部屋で過ごした年月は長くて有益だった。ライフル銃と弾丸と手投げ弾を持て! このフィルムメーカーは壁に直面している。彼の次回作は、その外へとジャンプするだろうか?
※このエッセーは、マルセイユ国際ドキュメンタリー映画祭2007のカタログに掲載された文を改訂したもの。