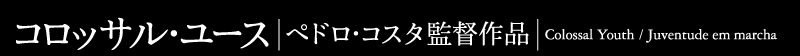
ポルトガル映画作家がリスボンの最下層、カーボ・ヴェルデ系移民へ
『コロッサル・ユース』には物語も虚構も脚本もないが、それでも理解や賞賛や解釈は可能だ。あらゆる形式を駆使し、あらゆる意味においてフィルムが語るのは、取り入れ=養子縁組(アドプシオン)のプロセスである。映画作家はカーボ・ヴェルデ島民のディアスポラをその最底辺まで自分のなかに取り込み、今回はさらにリスボン郊外の流れ者、ヴェントゥーラを仲間に引き入れる。かれを自分の映画の俳優に、しかもその中心人物に、自分の英雄にしようというのだ。このヴェントゥーラもまた、幾人かの脇を固める人物を「わが子」とする――この「子供たち」は慣例的にかれを「パパ」と呼ぶだろう――ことで、養子縁組の手続きを反復する。この「子供たち」というのは、おしなべて麻薬中毒患者、ホームレス、失業者、社会に見捨てられた落ちこぼれといった人々なのだが、実のところ、それよりもまず、とても魅力的な人物たちであり、かれらもまた仲間に加わるのだ。さらに、このフィルム自体がかれら登場人物たちの紡ぐ物語を、シャツを羽織るように身に付ける、あるいは、窮するあまりぼろぼろになりそうな眼と心を守ってくれる、悲しいフィクションの断片をそのなかに取り込むということもある。
まるでなんでも食べてしまう獣だ。なるほど、そうかもしれない。「われは他者なり」云々、とでも言いたげである。もちろん、人間ペドロ・コスタの「われ」が、ランボーとフロイトを足したものほど強靭で賢いというわけでもないだろうし、わたしたちの誰よりも西欧人の自我観という宿命から逃れているというのでもない。だが、作業に入った映画作家の「われ」はまるっきり別、その本領は、その宿命に抵抗すること、あたり一面いたるところに垂れ流しになりそうなこの自我を1グラムも滲み出させないようにすることにある。この「われ」は他者そのものであり、あるいは、そうでないなら少なくとも、他者と相互嵌入し、他者に宿り、他者に生成することに最大限の力を傾けている。しかしながら、コスタが他者のなかに自ら身を投じ、他者とともにわたしたちをそのなかに取り込んでしまうというとき、それは、ユネスコ的な共感とは程遠い、むしろ視線による食人とも言うべきかたちをとっている。食人鬼としての映画作家は、観客の注視のもと、獲物のもつ純然たる美、偉大さ、黄金やダイヤモンドのごとき人間的な価値を貪り食い、自家籠中としてしまう。1匹の獣ほどの敬意も払わず、しかしそのぶん的確かつ公正に、また獣のように優雅なしかたで。たしかに、こうしたものを丸ごと飲みこんだコスタの映画には、なにやら重苦しく、ごつごつしていて、巨像のように近寄りがたいところがある。似非ロード・ムーヴィーの対極、偽の軽快さ、風に乗ってどこへでも行けるというような魔法の靴とは、まったくの正反対だ。鉛の靴を、動かないことにおいて擁護すること、それがコスタの映画である。さらにおもしろいことに、この圧倒的な、超重量級の部隊は、垂直運動の映画、上昇運動であなたがたを地面に貼り付けたように動けなくしてしまう映画を作り出す。コスタは水平運動とは無縁で、そこには水平線もない。あるのは、動かず曲がらず、大地から雲、動物から人間、自然から芸術、フレームからタブローへとまっすぐ伸びた一本の筋だ。たどり着くのはなかば空想の美術館、そこでヴェントゥーラは最後に奇妙な「旅」をすることになろう。
残るは、あの狂おしい時制の錯綜、『コロッサル・ユース』がわたしたちを釘付けにする時間性の問題だ。コスタがショットに与える、この持続を越えた持続とは、何なのだろうか。とりあえず観客への勧告をひとつ、なすべきことはこれだ。もはやどこにも居場所などない人々のなかに、自分の居場所を見つけること。居場所がないというのは、自分たちの住むスラムが取り壊された人々のことだ。いかなる想い出の痕跡ももたないアパートに移住させられた人々のことだ。ところでその想い出、かれらにはそれしかないのだ。だから、かれらは話す。自分たちではどうにもならずに過ぎ去ったさまざまな歴史の糧を得て、思い出を反芻するために。コスタは、それを前にここしかないというフレームを決めて記録していくだけだ。かれが時間を自在に操れるわけでも、シークエンスについてひとりで決めるわけでもない。なるようにしかならない、というわけだ。この時間の流れは、それを見届けるひとは何もできずに見届けるだけなのだが、といってけっしてひとを不安がらせるだけのこけおどしではない。それは共有された経験のあるひとときを切り取ったものなのだ。その時間の流れ方は私たちの慣れ親しんだものとは真っ向から対立する。すでに『ヴァンダの部屋』で、麻薬中毒患者の目を背けたくなるような堕落ぶりを前に、自分の身をどこに置くべきか思案していたもの、こうした意欲ある観客、フィルムが進むにつれそこに溶け込むほど浸ってから帰りたいと欲する観客であれば、時がたつにつれコスタの映像のこうした時間の処理が目指すものがわかってくる。ヴァンダを映したショットは、わたしたちの皮膚に刺青のように彫りこまれて消えない。ショットの考えられないような持続が上映後も作用して、想い出させるのだ。このときから、ヴァンダは存在し続ける。永久に、生き続けるのだ。こんなふうにコスタがヴェントゥーラと粘り強く我慢比べを繰り返すそのやりかたを見届けるというのは、後方で砲台からのんきに眺めるだけの演出法などでは味わえない、観客とスクリーンを引き裂かんばかりに打ち砕かれた生とのあいだに、なんらかのやり取りが起こるというまさにその感覚を感じ取るということなのだ。
もしかしたらそう思われているのかもしれないが、コスタがわたしたちに突きつける要求は、ヴェントゥーラのもとで、ヴァンダのもとで、つまりは人として最もみじめな環境へ上映のときを過ごしに出向かうことだけではない。逆に、コスタはこのひとたちをわたしたちの裡に招きいれているのだ。ひとはかれらを動くことのない、凝固してしまって、石化した聖像のような存在だと思っている。実のところ、かれらは、その光のスペクトル、その影も含めて、移りゆきのさなかにある。無知の状態、まったくの暗黒から、感知できないほどではあるが、光のほうに這い出てきているのだ。映写機のまばゆい光線にむかって。それに、この登場人物たちは「上っていく」のであって前進はしない、むしろその場でもごもごと言葉を発する存在であった。何度も何度も、ヴェントゥーラが死んだ恋人に宛てた詩が、そこから外に出ることのない時間の円環を閉じに回帰してくる。「お前に10万本の煙草を贈りたかったのに、両手で数えきれない流行りの服、車もひとつ、お前がずっと憧れていた溶岩のかわいい家に、はした金で買う花束も、でも、なによりもまず、うまいワインを1本空けて、僕のことを想ってくれ。素敵な言葉を身につけるよ、僕ら二人のためだけの、僕らにぴったりの言葉を、まるでやわらかい絹のパジャマのように。」僕ら二人のためだけの。コスタのフィルムを前にして、わたしたちは自問しないだろうか。二人のうち、このいなくなってしまった方がどちらで、また、ずっと引き入れられないまま残されたものはどちらなのだろうか。