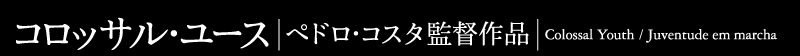
ペドロ・コスタの健全ならざる麗しさ
これほど美しいタイトルがあるだろうか。ちょっとしたブラック・ユーモアをこめつつ、カーボ・ヴェルデの共産青年同盟とのつながりを示すそのタイトルを冠するのは、あのポルトガルの映画作家、そのラディカルな姿勢から映画という惑星の最果てに位置付けられる作家の、極地にふさわしく荒涼としたフィルムである。大がかりな国際映画祭で疲れきった身には応えるペドロ・コスタの作品を前に、この寒さに震えることなく落ち着いて見ていられるはずもない。長大で、観客への要求が高く、スペクタクルの通常の法則を信じないがゆえに、待つことの意義を再検討していた70年代の人々であればともかく、それよりも数段素朴な現代の観客の忍耐力には、きびしい試練を課すことになるのだ。その試練をくぐりぬけたものには、そのかわりに、作品に端を発する美しいという感覚が訪れる、それがペドロ・コスタの映画だ。
『コロッサル・ユース』はしたがって、今年度カンヌ映画祭の、優れてハードコアをなす作品である。『骨』(1997)で始められ、『ヴァンダの部屋』(2000)に引き継がれた方法論を、映画作家はこの作品でも踏襲している。撮影対象は、リスボン市外のスラム街、フォンタイーニャス地区に住む、大半がカーボ・ヴェルデ系の人々、首都において内側から排除されたかたちになっているこれら旧植民地の民のそばに居続けること、それがこの作家のやり方だ。ここでは貧困、ドラッグ、暴力が猛威を振るっている。それゆえ映画表象の問題も、より鋭さをまして提起されることになる。それを10年、この地に身を擦るように寄り添い、この地から自身の作品の糧を得てきたコスタは、健全とは言いがたいがゆえに(貧困を美化しているのか、それとも美的に優れているからこそそう見えるのかという)議論を呼んだ、麗しき演出のスタイルによる庇護の下であれ、10年積み重ねてきたのだ。こうした息の長さを目の当たりにして、自己をそこに投入する行為においてそれがいかに意味のあるものかを考えると、尊敬の念を抱かざるを得ない。
シリーズ3作目となる今作は、過渡期の作品、変遷を主題とした作品とも考えられる。取り壊しの進むフォンタイーニャス地区の不衛生な小部屋を離れて、コスタは慣れ親しんだ登場人物の幾人かとともに、国が移住先として用意した近代的な柵のなかに冒険に乗り出すのだ。
そこでは、あのすばらしいヴァンダ、いまや母親となり、苦痛にとらわれながら麻薬中毒治療を続けるヴァンダにも再会できるのだが、それより今回の収穫は、ヴェントゥーラの発見、スラム街最後の抵抗派のひとり、第四世界の粋人にして、巨大なウサギ小屋に生きたまま自分を閉じこめんとする役人たちの悩みの種という、とんでもない人物の発見にあり、軸となる人物にも変遷が見られる。
変遷の最たるものはなによりも光の調子であり、地下墓所の薄光のなかで、ひとが生ける屍のように漂っているゲットーから、新しい街区のまばゆい白さへ、がらんとしたモデルルームで、かれらをガラスの中に閉じ込めて動けなくしてしまうかのような真新しさへと、明暗が大きくシフトしている。ここでもそこでも、この新興団地の壁が苛酷なまでに光のコントラストを強め、どこへ行ってもうんざりするほど空は消えうせ、どこへ行ってもメランコリーの黒い太陽が空を覆う。そんなわけで、闘争は続くのだ。ここの人々を消滅せんとする体制と、それに抵抗するかれらのような存在がこの世界にいることを明示し続ける映画作家との闘争は。だから青年よ、前へ!