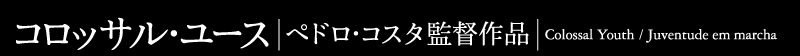
今年のカンヌで上映された映画の中で、最もショッキングだった瞬間は、ジョン・キャメロン・ミッチェルの『ショートバス』で、ポール・ドーソンが自分の精液の源を吸った時ではない。ギレルモ・デル・トロの『パンズ・ラビリンス』で、セルジ・ロペスが家庭用の裁縫道具で、切られたばかりの自分の顔を縫った時でもない。またジョルジ・パールフィの『タクシデルミア ある剥製師の遺言』で、勃起がブロートーチになるとか、早食いコンテストが大量の嘔吐で終わるとか、巨大な猫たちが破裂した飼い主のはらわたをむさぼり食うとか、自分を剥製にすることが映画の血みどろのフィナーレになるといった、ボロヴツィク的な刺激の盛り合わせでもない。これらおどろおどろしいシーンのどれを取っても、ペドロ・コスタの『コロッサル・ユース』で突然、リスボンのカルースト・グルベンキアン美術館にあるルーベンスの絵画『エジプトへの逃避』のショットが登場するという、完全に混乱をきたすパワーにはかなわない。映画の後半で、薄暗くて荒れ果てた部屋の中で声高に交わされる、終わりがないように思える会話の連続に差し挟まれる形で、このオランダのバロック期の傑作が、静かで華美な設定で突然登場したことで、映像および音の迫力が増した。これは感覚の襲撃といえるショット・トランジションだ。(モーリス・ピアラは、このようにめまいを起こさせるような編集のプロだった。)しかし、この映画の最初の長いモノローグの間、プレス試写会を1時間早く逃げ出した大勢の人々は、コスタのフォーマルな大成功である『コロッサル・ユース』が、カンヌがますます反目している、ゆっくりした、大いなる集中力を要する作品であるということを味わえなかった。コスタの映画に比べれば、カンヌの他の多くの作品は迎合と甘言だった。
この48歳になるポルトガル人の監督は、酷評には滅多に驚かない。彼の支持者たちは長年に渡って、暗いカルト信者、ポルトガルのポルノミゼリアという彼の特定ブランドの、まじめくさった帰依者として冷笑されてきた。コスタとうまくフィットするのは、マノエル・デ・オリヴェイラやジョアン・セサール・モンテイロなどの名高い同国人ではなく、ハンガリーのベラ・タールやドイツのフレッド・ケレメン、それにリトアニアのシャルナス・バルタスといった、汎ヨーロッパのミゼラブリスト集団だ。彼らのビジョンは、それぞれ異なっているが、長回しと絵画的な構図の傾向、荒涼たる風景と、苦悩にさいなまれ人生に疲れた顔を好むこと、存在することは地獄だとするドストエフスキー的感覚を分かち合っている。
コスタは、鮮烈な長編劇映画デビュー作『血』(1989)でのロマンチックな詩的感情や、主にカーボ・ヴェルデ諸島が舞台となっている、ジャック・ターナーの影響を受けた『溶岩の家』(1994)での夢想を捨て、時間をかけて今の引き締まったスタイルに到達した。『血』は『夢の戯曲』の白黒版で、音楽はストラヴィンスキーを使い、『恐るべき子供たち』『狩人の夜』『ミツバチのささやき』に帰着する、2人の兄弟が幼稚園の先生と逃亡するという不思議な物語だ。だが『コロッサル・ユース』で完結する3部作の1作目である『骨』(1997)では、夢のような暗示を含んだアプローチが、ブレッソン的な手法(省略的な編集、エスタブリッシング・ショットの欠如、登場人物には聞こえない音楽、抑揚のないセリフ回しの無表情な素人の俳優たち、映像に代わって画面の外の世界をほのめかす音、物と体と空間を正確に実物主義的に描写)に取って代わる。コスタはそういったアプローチを、まったくブレッソンらしくない物や設定(リスボン郊外のスラム街での貧しいみじめな人生)に適用した。
『血』が持っていたものさえ剥ぎ取った『骨』という題名そのものが、この映画が得ようとしている骨のような簡素さといったものをほのめかしている。ダルデンヌの『ある子供』(2005)よりずっと以前に、コスタは自暴自棄な10代の母親から生まれた赤ん坊の物語を語っている。この母親のボーイフレンドで、同じように若くて無表情な男が、赤ん坊を物乞いの道具として使い、のちに売ろうとする。最初は彼に多大な親切心を示した看護婦に、その後は売春婦相手に。(彼は、売春婦とセックスしている間、愛らしい赤ん坊をベッドの下に置く。)この映画の絶望感は、非常に強烈で濃密だ。ヒロインが自分の存在を6つの言葉「寝て、起きて、寝て、起きる、みじめな、生活」に要約した、ジェルジ・クルタークの『カフカ断章』のうらさびしい表現の1つを思い起こす。赤ん坊の母親は、一度ならず二度までも、最初は自分の子供を道連れにしてガス自殺を試みる。彼女の親友である清掃婦も、父親に復讐するためにガスレンジを使う。
コスタの明暗のむらがある構図と省略的な編集のおかげで、見る者は時に、削り取られた出来事とあいまいな関係という割れ目をなんとか渡らなければならず、そのような手法は、彼が好むブレッソン効果(手や鍵や戸口の大写し、人物が画面の外に出た後、時々カメラがしばらく止まっている、画面の外から聞こえる音が隣接する空間を示す)がそうであるように、苦しさを暗示している。だが『骨』は禁欲的というよりは官能的、否定的というよりは悲痛だ。コスタが、彼のみじめな登場人物たちを情感を込めてクローズアップにすると、ほとんど幸福に等しくなり(夢見るようなまなざしをした、ソフトな長髪の父親は、ベリーニが描いた黙想する聖母マリアたちの1人を思い起こさせる)、すばらしい照明が、赤いドレッサーの上に置かれた写真と鍵とクシャクシャにされたタバコの箱を写した2つの対称のショットを、色使いに特徴がある画家が描く静物にする。またコスタには、きらびやかさがない。彼は、通りを歩く父親の長くて手の込んだトラッキングショットを明らかに楽しみ、目立たせるための効果として、極端なシャロウ・フォーカスを2回使った。彼のあからさまなヴェリズモは、登場人物間の関係を確立するため、時にあり得ない偶然へと逸脱する。それに彼は、プロの俳優の起用を完全に放棄したわけではない(例えば売春婦役のイネス・デ・メディロスなど)。コスタは『骨』では、ゴダールが「この物語の美しい土地」と呼んだ国のパスポートを、まだ身につけている。
コスタは次の映画で、その国を完全に捨てる。彼の代表作であり、この10年間で最も優れた映画の1本である『ヴァンダの部屋』(2000)だ。『骨』に不満だったと言われているコスタは、彼の女優の1人で、前作で復讐する友人役を演じたヴァンダ・ドゥアルテの物語を語るために、取り壊されつつあったスラム街の舞台に戻る。コスタの当初のプランでは、『ヴァンダの部屋』のすべてを、題名の由来となった彼女の寝室を舞台として撮るはずだったが、彼は賢明にもその舞台を、麻薬常用者や酔っ払い、もしくはギリギリの生活をしている人々の孤独な世界、ブルドーザーとジャックハンマーによって包囲され、まもなく消える運命にあるフォンタイーニャス地区全体に広げることにした。その結果である3時間のポートレートは、濃厚な充実にあふれている。控えめであり合唱的でもあり、手法はミニマルだが、ビジョンは大きい。『骨』での気取りを捨てたコスタは、厳格で内面的で非常に観察力が鋭いという、彼独自の厳格に共感的なスタイルに到達した。すべてが固定されたデジタルカメラで撮影されている。人物が画面を出入りし、通り過ぎる。そしてすべてのシーンにおいて、明らかにすぐ近くにいるけれど、限られた映像の中では姿が見えない登場人物の声が、画面の外から聞こえる。スラム街のほら穴のように暗い住まいの中でも、自然光だけを使って撮られた『ヴァンダの部屋』は、『骨』が志していた簡素さを達成した。加えて、前作の安易な絶望は、この映画で見つけた真実の簡素さとは違う。登場人物の1人が言っているように、これらの人々にとって人生は"屈辱以外の何ものでもない"かもしれないが、彼らの周りで文字通り取り壊されている世界での、お互いに希薄な関係の中で、彼らは彼らの真価である優しさと気高さを高らかに示している。
ヴァンダと彼女の妹ジータは、ハエが飛び回る部屋の中でヘロインを吸い、時には古い電話帳のページから麻薬の残りをこそげ取る。ずっと前から依存症である2人は、全編を通して吸って、こそげ取って、また吸うが、なんとか生きている。例えばヴァンダは、家から家へとキャベツとレタスを売って歩くことで生計を立てている。自分の赤ん坊を売ろうとして、その後、死んだその子をゴミ箱に捨てた女性について数回言及した後(『骨』に登場する自暴自棄な母親ティナのことと思われる)、この映画は、通常の物語の形のほとんどすべてを捨て、フォンタイーニャスの日常生活をシーンの合間に入れるという、小津の影響を受けた"ピロー・ショット"を句読点として、ヴァンダ、彼女の家族と隣人たち、地域の男たちのシーンを、表面上はランダムに集め続けている。これらの映像に伴うのが、悪魔のような解体用の機械が砕き、打ち壊し、すりつぶすシーンであり、この映画には、薄い壁を通して絶えず聞こえる犬や子供たちや大きすぎるテレビの音、口論や咳や不平の声といった、豊かな音の風景がある。(コスタは概して、登場人物には聞こえない音楽をバックに流すことを避けるが、皮肉な対照的要素の"アクシデント"に対して優れた耳を持っている。ヴァンダのみすぼらしい世界で、しばし聞こえる曲には、『キャッツ』の『メモリー』や、スナップの「I've got the power(私にはパワーがある)」という皮肉な歌詞、それにあの最も華麗なバッハのアリアで、ロ短調ミサの終わりの方の歌詞「神の子羊、世の罪を除きたもう主よ」などがある。)
『ヴァンダの部屋』は通常、ドキュメンタリーとして分類される。そう分類した方が都合はいいが、それに賛成するのは難しい。コスタが驚くほどの詳しく登場人物たちを描いているのは(彼らが演じているのは自分自身だが、それでも彼らは登場人物なのだ)、多くのリハーサルの末にやっと実現したものだ。コスタは長年に渡って、フォンタイーニャスのコミュニティーのメンバーたちを助け、一緒に仕事してきた。彼の"俳優たち"が、彼の(小さくて出しゃばらない)カメラに身を任す自然さと率直さは、明らかにその連帯に由来する。瞬間は盗まれるのではなく、練習されてとらえられ、『骨』の物語上の省略とかけ離れてはいない形でまとめられている。例えばヴァンダの姉ネラの刑務所入り、ジェニーという麻薬ディーラーの死、麻薬から抜け出したペドロという麻薬常用者の運命など、バラバラな物語がだんだんとつながり、明らかになってくる。ペドロが最初に登場するのは映画の始まりの方で、彼の体が画面の右手下に、きつく押し込められている。彼は燃えるような赤とオレンジ色の花を抱えていて、このショットは不可解で気まぐれで、他の映像や物語とは関係ないように見えるが、彼は約1時間後に、彼とヴァンダがぜんそくについて話す長くて感動的なシーンで、突然、再登場する。このように故意に断片的な手法で進むドキュメンタリーは少ない。
またコスタは、真実のニセのシニフィエとしてのドキュメンタリー風な"見かけ"には、明らかに興味を持っていない。初めてデジタルで撮ることで、自由が得られる反面、精密さが制限される中、コスタは照明と構図をいじらずに、明白に美しくなるよう努めた。暗い明かりのもとでかすかに光る、壁に立てかけられた松葉杖、解体の最中に体を洗う裸の男と、彼のひょろ長い茶色の体から出るたくさんの湯気、交差する鏡を使った2つの顔のキュービスム風な配置、人の住まない部屋の詩的なモンタージュ、明るい緑色のバッグに寄り添う、使い終わったライターでいっぱいの赤いプラスチックの容器、2つの青い立体の照明の並置(1つはチカチカするテレビ画面、もう1つは家の闇の中に浮かぶ、遠くの部屋の開いているドア)などだ。ほとんどはコスタのスラム街の室内の薄闇で見えず、暗いせいで時には顔の見分けがほとんどつかないが、彼はデジタルの暗さをうまく避け、例えばロウソクの光で撮った麻薬常用者たちのシーンを、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの、より落ちぶれた人たち版とすることに成功した。
『骨』と違って『ヴァンダの部屋』では、これら人生の閉塞と貧困が描かれていて、真の絶望が感じられる。1人の男は「悪人は死なない。お人好しが死ぬ」とはっきり言い、ヴァンダ自身も「私たちは本当に貧しい国、最も悲しい国に住んでる」と言うが、彼らの過酷なその日暮らしの生活の中では、絶望はぜいたくに見える。コスタの徹底的に個人的判断を避ける手法では、麻薬依存症は単なる事実として扱われる。腕から針をぶら下げた男が、自分の掘っ立て小屋を掃除し続け、もう1人の男は何気なく、麻薬を注射した後にゴミを捨てに行くと言う。ヘロインがヴァンダに及ぼした最悪の影響は、彼女の喘息の咳の発作のようだ。『ヴァンダの部屋』にはユーモアもある。ブロンディというあだ名の麻薬常用者が、いつまでも髪をとかしていたり、もう1人は老婦人に物乞いするため、5階まで階段を上ったのに、ヨーグルトを2つしかもらえなかったとこぼす。彼は階段を下りながら、少なくともそれがイチゴ味であるよう祈るのだ。2人の麻薬常用者が自分の血腫について、まるで主婦がレシピについて話すように、「俺は歩く血腫だった」などとしゃべっている。ヴァンダとジータの母親は、まるで彼女たちがシンディとマーシャ・ブレディであるかのように、部屋を片付けろと叱る。彼女たちは、マリファナのにおいがする煙を吐きながら口答えする。最後のシーンでは、ジータが小さなピストルを振り回しながら、『ポリスアカデミー』で女優が巨乳の谷間から、同じようなピストルを抜いたのを見たことについて話す。でも笑いは続かない。ジータはすぐにマリファナで恍惚となってベッドに横たわり、彼女とヴァンダの世界を壊しているジャックハンマーの音が近づき大きくなる。彼女は、目が見えない子供と遊ぶために、恍惚とした状態から目を覚ます。その後、壊されたビルの残骸の長いショットが続き、スクリーンが暗くなる。それはフォンタイーニャスの住民が幽霊になったと思えるような、突然で吸い込まれるような闇だ。
『コロッサル・ユース』では、これら住人たちが、カサル・ダ・ボバという新しいリスボンの地区に移され、ヴァンダを含む多くの人が、きちんとした低家賃の住居に住んでいる。今ではメタドンを服用しているヴァンダは、まだ苦しいぜんそくに悩んでいる。彼女が映画の最初の方で、かん高い金属が震えるような哀れっぽい声で、子供の出産について長いモノローグを始めたことが、カンヌでの多くのプレス関係者の退席につながったことは間違いない。しかし『コロッサル・ユース』の主人公は彼女ではなく、年取ったカーボ・ヴェルデ人の労働者ヴェントゥーラだ。映画の初めで、彼の妻(クロチルドという名前は、ヴァンダが『骨』で演じた役名と同じ)が彼を捨てる。魂をなくした、名前にふさわしいヴェントゥーラは、あちこちをさまよう。彼との実際の関係が決して明らかにされない数人の"子供たち"の話を聞きながら、家から小屋へ、部屋から部屋へと渡り歩く。『ヴァンダの部屋』の合唱的なクオリティが、『コロッサル・ユース』で増幅されている。悲しむ者と立退かされた者たちが、ヴェントゥーラに自分たちの話を素朴な多声音楽のように語り、クロチルドに戻ってきてもらうために何をするかと、ヴェントゥーラが何度も繰り返す節回しが、彼らの定旋律だ。(コスタはこれのために、フランスの超現実主義者ロベール・デスノスが、ブーヘンヴァルトから送った手紙を引用する。この手紙は『溶岩の家』の生みの親でもある。)この映画のポルトガル語の題名『Juventude em marcha』(『溶岩の家』で、滅多にない喜びの瞬間に発せられたフレーズ)の皮肉な期待とは裏腹に、カサル・ダ・ボバで若さ(ユース)が前進することがないのは明らかに思える。
ヴェントゥーラの子供と言われている人たちそれぞれが、コスタに自分たちの話を語った。その多くはバラバラになった家族や、失ったチャンスについてだった。彼は15ヵ月以上に渡って320時間分(撮影比率としては、確かに記録的だ!)の映像を撮影し、登場人物たち相手に厳しいリハーサルをして、自分が望むせりふ回しを撮るために、時には30テイクも費やした。(彼は、この点においてブレッソンに似ているが、ブレッソンの狙いは完全な中立であり、コスタの狙いは様式化されたナチュラリズムである。)コスタは『ヴァンダの部屋』のビジュアル・アプローチを保っているが、それをさらに制限している。固定されたカメラと自然光で撮影された『コロッサル・ユース』のテイクは、しばしば長回しされている。(コスタが『骨』で好んだ、ブレッソンのようなドアの鍵や手や不完全な肉体のクローズアップが戻ってきている。)コスタは時に、ヴェントゥーラが間違えてヴァンダをジータと呼ぶなどの間違いを、そのままにしている(ジータは『ヴァンダの部屋』の後、死んだことが明らかになる)。彼は、ヴェントゥーラが重い足取りで歩く横で、並んだビンが揺れるなどの、些細だが面白いディテールをカメラに収めることを好む。同じような偶然と正確さのミックスは、オーディオ・トラックにも適用されている。イライラするような風、のこぎりの攻撃的な高く鋭い音、アパートの中でシューシュー音を立てるガス、テーブルにたたきつけられるトランプのピシャッという音などは、1つか2つのマイクでDATに録音された、ふと出くわした音の濃密な堆積だ。
『コロッサル・ユース』では、『ヴァンダの部屋』にも増して美が追求されている。これはある意味で、光と光の欠如についての映画だ。荒々しく壊されて、ペンキがはげ落ちた室内で、ほとんど浸透していない光が移動し、集まり、遠のく。コスタは、違う光の中で同じ構図を繰り返すことによって得られる効果に注目している。(彼は『ヴァンダの部屋』でも同じような効果を得るために、日食を使う。)比較的少ない屋外のショットでは、強い日光のせいで、白いアパートメント・ビルが構成主義のレベルに達している。コスタが、『コロッサル・ユース』は成瀬巳喜男の映画に影響を受けていると言った時、人はまず、成瀬の逃げ場を失った登場人物たちの貧しくて陰気な人生を思い浮かべる(彼らはコスタの映画の登場人物たちの次に、比較的気楽にやっているが)。しかし美術史家アンドレ・スカラは、日常を描いた成瀬の映画は、17世紀のオランダの風俗画とその形式の要素に似ていると洞察している。荒廃しているが美しく撮られたコスタの室内では、窓や開いたドアが光源となることが多く、それらは同じオランダの風俗画の室内の現代版に見える。彼のクローズアップはトロニーと呼ぶことができる。コスタの構図(例えば病院のベッドにいるパウロ)は、しばしば低めで、登場人物たちが画面の下3分の1に位置して、彼らの上には大きな白い壁がある。それが最も顕著なのが、ヴァンダとヴェントゥーラとヴァンダの夫がダイニングテーブルを囲んでいて、映像の上方真ん中を、繊細なシャンデリアが占めているショットだ。(ヴァンダの後ろにある奇妙で場違いの地球儀は、非常にフェルメール的だ。)
コスタは、ジャン=マリー・ストローブとダニエル・ユイレの映画制作チームが、自分たちの映画『シチリア!』を編集する様を描いた優れたドキュメンタリー『映画作家ストローブ=ユイレ/あなたの微笑みはどこに隠れたの?』(2001)を作った。彼らの実物主義の美意識の影響は、『コロッサル・ユース』全編において明らかに見られる。特にその綿密な映像が、ほぼ真四角である旧式の1.33サイズで撮られていることにおいて。現在、この時代遅れのサイズで上映する装備がなされた映画館は、もはや少ないのだから、現代の映画には文字通り不適応なのだ。『コロッサル・ユース』でのモノローグは、最近のストローブとユイレの映画、例えばイタリアの農民たちが、風景の中で立ち上がって主張する『労働者たち、農民たち』の影響を受けているように見える。コスタが一連の室内のショットの合間に入れた公園、木、水、太陽、鳥、ハイウエーなどの、短くて、都会のオアシス的なショットは、『ヴァンダの部屋』ほど小津的ではない。それらはストローブとユイレが『アンナ・マグダレーナ・バッハの日記』(1968)で、18世紀の室内シーンの合間に挿入した、海や流れる雲のシーンに、より似ている。
カンヌでは一部の批評家たちが、『コロッサル・ユース』は魅力のない人々だらけで退屈であり、スラム街を芸術的に見物してるのであって、映画とは言えないと不満を述べた。俳優がいない、カメラの動きがない、音楽がない、だから映画ではないというのが、その理屈だ。忍耐が希少価値とされるカンヌでは、最も安易な反応は嘲笑であり、ゆえにコスタのすばらしい作品は、予想どおりバカにされ無視された。しかしヴェントゥーラは、カンヌの他のどの登場人物よりも記憶にしっかり残った。それに彼が体を丸くして座り、我々から顔をそむけて古いポータブル・レコードプレーヤーを聞くシーンや、自分たちの運命について座って考えるために、テーブルの表面を一心にひっかいている男の手を静止する見事なジェスチャーなどによって湧き上がる感情に匹敵する映画は、カンヌでは他になかった。ヴェントゥーラは、この映画の忘れられない最後の長いショットで、ヴァンダの赤ん坊の世話をしながら、ベッドに横たわっている。我々は"ヴァンダの部屋"に戻ったのだ。コスタは意図的に、『ヴァンダの部屋』でのジータと子供の最後のショットを繰り返している。つまらない監督なら、老人と赤ん坊を"人の年齢"といった絵画的な場面にしたり、"人生は続く"という月並みな場面にしただろうが、コスタの最後のロングテイクは、単に不動性と脱力感、過去に止まってしまった人生の感覚を集めている。それは静かな力で人の心を打ち、『コロッサル・ユース』は最後には、まさに途方もないもの(コロッサル)、アルテポーベラの大作となった。