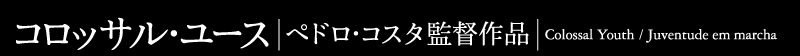
――――『コロッサル・ユース』はヴェントゥーラを中心に、その周りをめぐるようにつくられた作品です。はじめからこの人物を軸にしようと考えていたのでしょうか。
リスボン北西に位置するフォンタイーニャス地区、わたしが『骨』を撮影したその地区はもうありません。『ヴァンダの部屋』を撮っているときにはすでに取り壊しの真っ最中でした。そこに住む家庭はずっと遠くの新興住宅地、今回の作品で見られるカサル・ボバ地区に移住させられたのです。わたしは、これを機に歴史をさかのぼって、フォンタイーニャスにはじめてバラックを建て、暮らし始めた最初期の住民たちのフィクションを作ろうと考えました。
ヴェントゥーラとは、他の作品の撮影中に何度もすれ違っていました。アウトサイダーとしては最たるもののひとり、隠者にして破格のアウトローでしたね。いつもわたしのことを不思議そうに見ていました。わたしはかれと話をして、かれがこの地区に最初に家を建てた人々のうちの一人だと知ったのです。
かれは、リスボンに身寄りもなくひとりでやってきたそうです。話していると、少しずつですが、1975年から1980年のヴェントゥーラの生とこの地区の歴史が重なっていきます。かれはわたしに自分が抱えている困難、かつての恋愛についても語ってくれました。そこからヴェントゥーラをこうした過去の原型をなす人物にしようという考えが浮かんできたのです。
はじめは躊躇しました。作業中の事故で負傷中の彼が、撮影の苦行に耐えられるだろうか、とね。奥さんや子供たちと話し合いながら、少しずつ信頼関係を持つようになりました。
――――撮影はもう始めていたのでしょうか。
いや、撮影というほどのものではないですが、つねに小型のキャメラは携帯していましたよ。関係作りは徐々に進んでいきました。かれが言ってくれたこと、打ち明けてくれた秘密から、かれの考え、筋の通った話を見つけ出す必要があったのです。いっしょに飲みに行って、慣れさせるためにキャメラを回しました。キャメラが一台あるだけで、単なる友情で結ばれていた関係が、もっと複雑になるということをわかってもらえるようにそうしたのです。
わたしたちが頭に描いていた最初のシーンというのは――フラッシュバックのようなものですが――、バラックの中のシーンで、友達とふたりでトランプをしているというものでした。少しずつそのアイデアにとって変わっていったのが、かれが自分の子供たち――作中、実際の子供たちではないということがあっても、かれらの家を訪れるというものでした。そもそもわたしは、かれには自分も知らないような子供、いなくなったり死んでしまったりした子供たちが他にもいる、まだ知られていない女性も他にいるのではないかと思っていました。というのも、カーボ・ヴェルデやアフリカ系の出稼ぎ労働者の大半がそうですが、かれもまたリスボンでの単身生活がとても長かったのです。
企画が始まったのは、こうした下地があり、こうして過去と現在が混じりあっていったうえでのことです。また、他の人たち、ヴァンダや青年たちをまた新たに撮りたいということもありました。かれらにもまだ語るべきことがありますからね。かれらの生活は一変し、このひとたちと一緒に居続けるのがわたしにとっても重要だと思ったのです。
――――ヴェントゥーラには、なにか特有のもの、あなたの映画にこれまで見られなかったものがあります。ロマネスクな次元というか。
わたしはヴェントゥーラと出会えたという幸運に恵まれたのです。はじめは、わたしにとってこの地区はただの舞台装置でしかなかったのですから。わたしには、ヴェントゥーラを、ヴァンダを、知性にあふれ、優しく、荒々しい、悲劇的な「部屋の英雄」にする必要があったのです。かれらが何も持たない弱者だとしても、このひとたちは連帯の感情、ある共同体に帰属しているという感情を強く抱いています。たしかに、ここでわたしになんらかのエキゾティズムを見出して非難するひともいるようですね。貧困層の生活を美化しているとか、その生活をだしに宗教画のようなものにまで仕立てあげているとか。かなり早い時期から、わたしの頭には、ある共同体、小さな村落共同体の観念があったのですけれどね。フォードやウォルシュの西部劇に出てきそうなものです。ヴェントゥーラの偉大なちからは、かれが自分のうちにそんな地区を持っているということにあります。かれはとても無口な男だけれど、同時に古典期の作家のような雄弁さも持ち合わせています。三語もあれば、あるいはワンフレーズもあれば本質的なことを表すには充分なのです。
しかし、わたしがヴァンダや青年たちと接近して、いくつかの問題を共有するようになると、その分だけヴェントゥーラとわたしの間に、おそらくはわたしたちそれぞれがそれまで通ってきた道のりに由来する、ある根本的な溝が存在するようになりました。はじめはそのことで少し不安になっていたのですが、逆説的にこの溝がわたしたちを近づけることになりました。
――――準備段階では、ドキュメンタリーとフィクションの往還はどのように組み立てられていたのでしょうか。
過去のことにせよ、現在のことにせよ、事前にこうするというようなシナリオはとくにありませんでした。ヴェントゥーラは確固とした精神の持ち主なので、的確な演出がされれば、かれをそんな人物であると信じないなんてことはありえないのです。わたしは、ロマネスクの断片――かれの抱える過去、住みなれた地区、このバラック、ロマンティックな手紙にまつわる物語――と、新街区にやってきた人々についてのドキュメンタリー的な要素が、相互に補い合うような作品の可能性をおぼろげに考えていました。ヴェントゥーラとわたしはほとんど社会学的とも言えるような対話を重ね、続いてそれを、フィクションを構成するように変形させていきました。撮影に2年をかけて、しだいに考えも深めることができたし、過去と現在とでゆたかに照合しあうというところではとくにそれがあらわれていると思います。
――――『骨』から『コロッサル・ユース』へと進む過程で、あなたの映画作りとしては、サイレントからトーキーというか、せりふが多くなってきています。このように人が自分のことを話していくことをだんだんと受け入れていく過程は、登場人物がゆっくりとあなたの映画作りの上で力を持ってくる過程とよく似ていますね。
わたしはここで3本のフィルムをつくり、それらはみな、程度の違いこそあれ、同じ登場人物をめぐる、周囲10キロにも満たない地域でのことでした。『骨』の撮影ではじめてかれらの住む環境に入っていったときは少し重装備で、撮影用の機械も入れました。初めてのときはいつもそうですが、よくわかりもせずにやっていたのです。時間がたつにつれ、初対面の不信感も友情に変わっていきました。『ヴァンダの部屋』を撮ったのは、そんな前回の作品に対するちょっとした反動からだったのです。というのも、『骨』の撮影にはいくぶんか刑事もののようなところがあって、まるで足跡を採取して手がかりを追ってでもいるかのようでしたし、一度撮影をしてしまえばすぐにそこを離れてしまいましたからね。撮影が終わると、ヴァンダは困惑してわたしに言いましたよ、映画はこんな機械的なものじゃないってね。それで、ここにとどまってまた別の作品を撮るようにと提案してきたのです。いまではお互いに本当の信頼関係が築けたと思いますよ。
わたしには、映画作家であれば誰もがこんなふうに仕事をすべきだと思われることがあります。それは、あるアイデアや信念があって、それを動力にしてそこから仕事を始める、ということです。それがあってこそ、ある形にたどり着くことができるのであって、けしてその逆ではありません。
この点からすると、ヴェントゥーラとの出会いは決定的でした。かれと同じ目線に立ってみたいと思ったのです。撮影期間のあいだはずっと、目覚めのたびに心のなかで、わたしを欺くことがない唯一の存在、そこにいる唯一の存在、それがかれだ、と意識していました。ヴェントゥーラはわたしたちにいつでも大きな信頼を寄せてくれ、いつでも新しいアイデアを提供してくれました。
――――例えばどのようなことでしょう。
たとえば、こんなちょっとした政治に関する回想があります。ポルトガルにやってきた当時、かれはそれなりの給料をもらっていて、勤め先もありました。その後、1974年にポルトガル革命が起こります。わたしに語ってくれたのは、1974年リスボンで実際に起こった、カーボ・ヴェルデの移民たちの隠された歴史でした。かれもカーボ・ヴェルデやアフリカからきた他の多くの労働者も、この無血革命を恐れていたそうですよ。国外に退去させられる、でなけりゃ牢獄に入れられるんじゃないかってね。わたしは1974年5月1日のデモ行進を撮影したある写真集を見ました。驚いたことに、100万人規模のデモで、ひとりも黒人がいないのです。かれらはどこにいたのでしょう。ヴェントゥーラによれば、かれらは恐怖からかひとつになって行動し、みんなリスボンのある公園にいたのだそうです。革命警察や、熱狂してそれに続く若者たちが、夜になると黒人狩りに出かけ、何人かを木にくくりつけるということもあったようです。当時14歳だったわたしは、こんなことはまったく知りませんでした。ヴェントゥーラがこうした歴史をはっきり見えるようにし、またそのおかげで、わたしにはフィルムに収めることのできないこうした痛みを理解できるようになったのです。若者たちとのシーンでも、かれはこうした才能を発揮して、青年たちの苦悩を、年の功というよりは、父親の態度、何でも知っている賢者のような態度で聞いてあげています。
――――このように登場人物が話してくれたことが、具体的にはどのようにまとまっていくのでしょうか。台本がないとはいえ、演説口調とは言わないまでも、ときに他人事を話しているかと思えるくらい、じつに独特な節回しで語っていますね。
おそらくこうした話し方は、前作『ヴァンダの部屋』からきたものでしょう。『ヴァンダの部屋』では、わたしはまず聞くことからはじめたのです。それからわたしが興味を持った部分や興味を持った話を選択します。そうして選んだものを、もう一度ヴァンダに提示して言ってもらうのです。二度目ですから、声のトーンももっと他人事のような、冷ややかなものになるというわけです。ヴァンダは、ひとつひとつのことを違ったふうに言いかえる方がよいのか、フレーズを自分で修正していました。記憶を省いたり、選択したり、言うことをだんだんと濃縮していくのは、こんなふうに何度も撮影してはじめて可能になったものです。
『コロッサル・ユース』で「子供たち」を演じるのは、わたしがすでにこの地区で撮影した、あるいは友人になったひとたちです。かれらもひとりひとりが自分のシナリオを、たくさんの個人的な話を持ち寄ってくれたのですが、そのどれもがやや問題含みのものでした。こんなシーンにしようというアイデアから始めて、それを繰り返すことで少しずつ変えていきました。なんとか俳優としての訓練をしていくことはできましたが、なんの障害もなく、とはいきませんでした。せりふを覚えるのが苦手なひともいたのですが、絶対やめるとは言わないんですよ。どうなるかよくわからなくても、とりあえず一度やってみるという気骨があるんですね。こうしたことがみな、ゆっくりと変化していくのですが、もちろん時間はどんどん膨らんでいきます。時間が根本的な要素だというのは、そういうことなのです。
しかしこうしたことができるのも、少人数で、ヴィデオを使い、大がかりな手法をまったく使わずに撮影するということがあるからなのです。ルノワールの『河』を見ると、長い期間をかけて撮影したことがよくわかります。わたしも2年間は、毎日撮影するのがほとんど当たり前でしたし、撮影しないというのも、たんに誰かの具合が悪くて、いっしょに食事をしたり、話をしたりしているからというくらいいっしょにいることが当然だったのです。それは、ファスビンダーやカサヴェテスの撮影隊というよりは、ハリウッドのスタジオ体制の雰囲気に近いものでした。役人のルーティンのようなものですよ。ときに退屈で、ときに興奮する。みんながスタジオで待っているような気がするときだってありますよ。すべてがそこにそろっていて、俳優もいる、それが仕事ってもんだ、というわけです。
――――推察するに、こうした撮影手法はヴィデオを使ったことによってずいぶん楽になったかと思います。ところで『骨』から『ヴァンダ』、さらに『コロッサル・ユース』へ連なる道は、フィルムからヴィデオへの移行でもありました。
それはそうなのですが、わたしにもう少しお金があれば、16ミリでも同じことはできたと思いますよ。DⅤは、小さなものを見るため、全体というよりは顕微鏡のように微細なものを撮るために作られたものです。ヴィデオでは、風景や木々を本当の意味で撮ることなどできません。そうするには情報や細部があまりに多すぎるからです。DVに向いているのは、壁や顔、ものであれば一度にそれだけで撮るというようなやり方です。あるいは、進行が遅いときにも向いていますね。それは、求めるものが得られるまで毎日撮影しなければならないというときに持つべきものなのです。DVを使うと時間がかかるということをよく理解して、間違っても節約になるなどと考えてはいけません。この件に関して言われていることとまったく逆なのです。現にわたしは、ヴィデオで撮影するほうがリスクは大きいと考えています。35ミリで撮っているときは、もっと映画というものに、またフィルムという物質のゆたかさに守られているように感じられるのです。考えることはいつも同じ――どこに、どの高さに、どのようにキャメラを置くか――ですが、得られる映像の質は根本的に違うのです。小型のDVキャメラではほとんど丸腰も同然で、何にも守られていない危うさをかなり感じます。わたしにとってのDVの美点は、わたしをつねに喪失感を抱いたままにしてくれる状態においてくれるところなのです。
おそらく産業としての映画には不向きなほどペースが遅いのでしょう、わたしには1本のフィルムを5、6週間で作るなんてことはできません。ルノワールはかつて、合衆国での失敗は、自分が暢気すぎたせいだと言っていました。わたしにとっても、それなりのものを見つけるのには時間が必要なのです。わたしには、ヴェントゥーラが革命当時の話をしてくれるまで1週間かかるだろうとか、最終的にはその話は3分しか残らないだろうとか、そんなことは事前にまったくわかりませんでした。
――――『骨』から『コロッサル・ユース』に至り、登場人物たちはますます不動の力強さを獲得しています。フィクション部分は主にこの人物たちが語ったところによるものですね。
たくさんの話をしたり聞いたりしてきた、互いにある時間を共に過ごしてきたという事実にかかわるところです。ある言い方をすれば、この作品はヴィデオ・レターのようなものだとまで言うことだってできるかもしれません。ヴェントゥーラにも、他の人にも、どんなときでも自分の言いたいことを言うように、と要求してきました。たとえばヴァンダであれば、自分の子供、そして子供ができたことで起こった生活の変化について話したがります。それは、わたしに、あるいは観客に宛てられた手紙であり、ひとりひとりが伝えていくちょっとした私信なのです。こんな言葉がとても限られた空間のなか、部屋だとか、廊下だとか、ふたつのドアの間だとかを旅していくのを見るのが、わたしの楽しみでしたね。
ヴェントゥーラにしても、かれの場合はそのスケールの大きさとその動作だけで、さまざまな場面で何かをするという気にさせてくれました。かれこそが、他の人を導き、動かしていった張本人なのです。わたしの考えでは、語るべきことがたくさんあるようなフィルムを作るにしても、それほど多くのものは必要ありません。語るべきことは、壁やベッドが語ってくれるのです。ヴェントゥーラの信念、力強く感じさせてくれる信念はこういうものです。つまり、ひとが言うべきことがあるときには、よけいな飾りなどなくても、簡潔に言うことができる、ということです。
――――『コロッサル・ユース』にはロー・アングルが多く、アイ・レヴェルで撮影された『ヴァンダ』とは対照的です。これは登場人物をより不動なものとする、ほとんど古代神話の英雄のようなスケールを実現するための方法なのでしょうか。
じっさいにどういうことなのかわたしにもわからないのですが、こうなるはずだというような直観はありました。わたしにすれば、かれらはいわば英雄なのだから、そう思っているということがおそらく関係しているのでしょう。しかし、それにしても『ヴァンダ』には、動きそのものも、動きを思わせる空気もふんだんにあるし、瞑想的なところにしろ、あるというほどありません。
問題は、生を、路地を、部屋を、話す言葉をフィルムに収めることなのです。『コロッサル・ユース』は、フォードの描く悲劇、叙事詩のような重量感をもち、顔にすこし疲労感のにじむ開拓者たちを配した悲劇に近いものだと思います。ここに出てくる若者もみな、それなりに年輪を刻んでいるのです。
きっと、自分はヴェントゥーラの高みに至っていないという恐れが、いつもよりもロー・ポジションにさせたのでしょう。おそらくは尊敬の問題、かれが部屋に入ってくると、みんなが自然に抱いているような尊敬の念がそうさせているだけですよ。単純に言ってしまえば、それがかれを撮る最良の方法だったということでしょう。
――――こうしたロー・アングル志向が、ときにほとんど表現主義ともいえるような様相を呈する背景に、大きく影響していますね。
この作品には、おおきく異なる二つの背景が出てきます。ひとつは独特の色合いを持つ古い町並み、路地と内部との区別もつかないようなたぐいのものです。公的な場所であると同時に、私的な空間でもあったヴァンダの部屋もそういったものでした。それから他方に、壁になんの歴史も刻まれていない真っ白なアパートメントがあります。いま登場人物たちはここに住んでおり、それゆえかれらはゼロからやり直さなければなりません。人生で初めて鍵を持つことになっても、同時にそれは、人々が分断されるということでもあります。自動的に上や下に行ってしまう進路があって、同じ高さにいる以上、前にそれは見えないのです。
フィルムはかれらと同時にこのアパートメントに入っていきました。ここの壁が何かを語ることができるかわかるには時間が必要だったのです。かれらだけでなく、わたしも途方にくれてしまいましたよ。
――――奇妙なことに、この新興団地ではほとんど空が見えず、真っ黒になっています、まるで空の青さが逃げ出してしまったかのように。
少しコントラストを強めにして、あと一歩でSFの世界、まるで別の惑星にいるかのようにしたかったのです。また、それと同時に、基本的にこの作品は室内劇だ、ということもあります。しかし、わたし自身のことを考えてみると、自分が映画のなかであまり好きではないものを拒否していたということなのかもしれません。空はまさにそういったものですから。空というのは、彷徨やら、瞑想やらの詩学とかいうものに、多少なりとも象徴的なかたちで結びつきがちなものです。思うに、そのせいでぼんやりした形態、あいまいな持続が生まれるのではないでしょうか。いかなるものにも曖昧であってはならない、というのが、わたしの信念です。さらに、わたしの撮ったものに人類がいないというなら、そこにはなにもないのだと、そんな気もしています。さて、わたしの考えでは、語るべきはつねに地面です。それがわたしの生き方でもあります。だからこそ視線はむしろ下のほうへ、あるいは人の目線の高さに向いていくのです。
――――親密さの感覚を生んでいたのも、かれらが以前住んでいた家の光と影の戯れでした。新しいアパートメントの、水槽のなかのような光とは対照的です。
これは、なによりも物理的な限界と経済効率の問題です。美術館のシーンを除けば、自然光で撮影しなければいけませんでした。電気の通っていない場所なので、照明はおろか、ケーブルもない、メイクもない、どんな機械装置もない状態で撮影されたのです。8枚とか9枚の鏡やレフ板を配置するだけで、光を取り込むのに使えたのはそれが全て、あとは窓やドアの近くで撮影するようにしました。これが、わたしたちがこの2年間、一度たりとも破らなかった原則です。自分たちがしていることの道理を失うことなく、使える手段とフィルムに収める物語とを合致させたままにしておかなければいけません。『コロッサル・ユース』では、古典的な作品づくり、正しい選択と、わたしにとって現実の限界である、技術上の限界を駆使して作品をつくることが重要でした。真っ白な団地を前に、人工的に架空の光と影の戯れを作り出そうなどとは思わないでしょう。場所がそんなことをまったく語っていないのだから。技術的な面から見ると、このフィルムにもヌーヴェル・ヴァーグのような側面はあります。ヌーヴェル・ヴァーグとは街路に出ること云々、とよく言われますが、実際にはそうともいえません。だって、たとえばユスターシュの『ママと娼婦』を見ても、そこに映っているのはアパルトマンと白い壁なんですよ。
――――よく古典的な映画作家を引用されますが、かれらにとってと同様、演出をどうするか決めるのは、具体的にどのようにするかを考えるということですね。
現に、考えるべきことは具体的なことばかりです。ヴェントゥーラの考え方にもそういうところがあります。かれは石工で、かれが考えるのは壁の建てつけがいいか悪いか、といったようなことです。新しい団地は、貧乏人のために作られた、いいかげんで、出来の悪いものだとかれは言います。かれがなくしてしまって悲しんでいるのは、過去、この白い壁のあいだに流れているはずの想像的なもののことです。だから、古い家のうす汚れた壁のほうが心地よいのです。
映画のショットはこの壁をつくる石材のようなものですよ。こんな野望があるのですが、最終的に、このフィルムが家のようなもの、欠陥もなく、人が住み、出て行ったり入ってきたりすることの出来る家のようなものであってほしいですね。